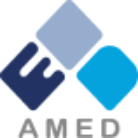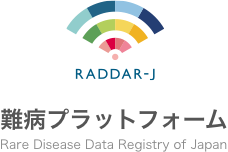| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
| 研究課題名 | 好酸球性副鼻腔炎における治療指針作成とその普及に関する研究 | |
| 研究代表者名 | 藤枝重治 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 好酸球性副鼻腔炎 | |
| 研究のフェーズ | 病態解明研究;疫学研究;ガイドライン・治療指針作成 | |
| 研究概要 | 好酸球性副鼻腔炎は、日本を中心とした東アジアで、好酸球浸潤の著明な難治性副鼻腔炎として2000年頃から増加してきた。この副鼻腔炎は、経口ステロイド薬のみが有効であるが、発症機序は不明であり、病態の理解も曖昧であった。2010年からの全国多施設共同研究で診断基準と重症度分類が出来上がった。これにより早期に診断がつき、かなり早い段階で手術を行い、厳重な術後経過観察をとることで鼻茸が再発しても早期かつ容易に外来で摘出できるようになってきた。しかし一方で、幾つかの施設別術後成績を比較するとかなりばらつきがあることもわかってきた。本研究では、内視鏡下鼻副鼻腔手術症例を多施設共同で電子登録し、経過を観察することで、治療成績と症例(フェノタイプ・エンドタイプ・所見内容・CT所見)との関連、術式との関連を明確にする。 好酸球性副鼻腔炎の保存的治療成績は本邦において存在しない。これまで好酸球性副鼻腔炎は少量長期マクロライド療法の効果がないとされていたが、実際の成績は不明である。そこで2018年からの3年間、電子登録システムを使用することで、マクロライド少量長期療法、経口ステロイド、鼻噴霧用ステロイド、抗ロイコトリエン薬の治療効果を判定する。また今回の検討は、介入試験ではなく、通常の診察内容を登録保存し解析するといった観察研究であり、患者への負担もない。電子登録システムは本研究事業で完成しており、現在研究分担者施設において、平成30年1月から入力ができるようになった。 手術における技能水準向上は、疾患克服のために極めて重要である。保存的治療の検討は、開業医・勤務医ともに重要な点である。プラセボ対照二重盲検試験のような高いエビデンスは無理であっても、全く治療効果が報告されていない好酸球性副鼻腔炎での成績が判明することは重要である。とりわけ軽症の好酸球性副鼻腔炎において、保存的治療効果を認められれば、手術が不要でQOLを保てることとなり極めて有用である。このように本研究の成果によって、患者のQOL向上と好酸球性副鼻腔炎の医療費抑制に貢献が可能である。 これらのことから治療指針を作成し、好酸球性副鼻腔炎が増加している東アジア(台湾、韓国、中国)の耳鼻咽喉科医に対しても、日本での治療方針および治療効果を発表することは、競争国もしくは指導国としても意義がある。 | |
| レジストリ情報 | ||
| 対象疾患/指定難病告示番号 | 306 好酸球性副鼻腔炎 | |
| 目標症例数 | 1000例 | |
| 登録済み症例数 | 100 | |
| 研究実施期間 | 2019年4月~2021年3月 | |
| レジストリ名 | ||
| レジストリの目的 | 自然歴調査;疫学研究;治験またはその他の介入研究へのリクルート | |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;DNA;組織 | |
| 収集サンプル数 | 300 | |
| 外部バンクへの寄託 | ||
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | 藤枝重治に連絡 | |
| 検査受け入れ情報 | ||
| なし | ||
| 担当者連絡先 | ||
| 福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 藤枝重治 sfujieda●u-fukui.ac.jp | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。